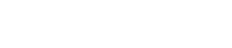車石

江戸時代
京都へ物資を運ぶ重要な物流ルートであった、東海道の京都・大津間の牛車専用道路(車道・くるまみち)に敷かれていた石です。溝の部分に車輪がはまるようになっており、石でできたレールといえます。ぬかるみ対策・道路保全のために約3里(12㎞)にわたって並べられた、物資輸送を支えた工夫でした。石の溝は車の通行によって削られたとの説が有力です。
車石は鳥羽街道・竹田街道にも敷かれていましたが、当時、全国の街道では車の使用は原則禁止されており、車道での牛車使用は京都周辺で例外的に行われていました。