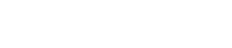江戸三度飛脚所看板

江戸時代
江戸時代の飛脚は、幕府公用の継飛脚、大名が用いた大名飛脚、町飛脚の主に3つに分けられます。町飛脚にもいろいろな種類が存在しましたが、そのひとつに17世紀紀半ば以降、江戸・京都・大坂の三都を結び、東海道を往来することから始まり、三都にそれぞれ飛脚問屋仲間を形成したものがありました。
これら三都の飛脚問屋仲間は、大阪所と二条城の在番武士(大番の番頭・番衆。一年交代で江戸から単身赴任した)が江戸との連絡を行うための輸送を請け負い、馬3頭で月三度の往復を行ったところから発展したものです。そのため彼らは「三度飛脚」と呼ばれ、やがて「三度飛脚」は定期便の代名詞のようになりました。やがて江戸の三度飛脚は定(じょう)飛脚と称するようになりましたが、大坂では幕末まで三度飛脚と称していました。